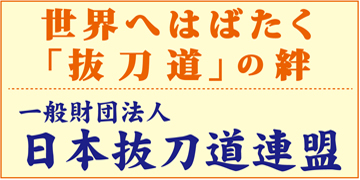1877-1947
現在、沖縄における三大流派の一つに数えられる上地流は、上地完文によって中国大陸で学んだ武術を基盤としたものとして、その誕生経緯は数ある沖縄空手の中でも異質なものといえる。そこには、創始者・上地完文の数奇な人生が大きく関わっている。
明治10年(1877)、沖縄島北部の本部半島に位置する本部間切伊豆味(もとぶまぎりいずみ)村に生まれた完文は、帰農した元士族の家である上地家において、屈強な体力を活かして家業を手伝う真面目で温厚な少年であったという。そんな完文が20歳となる明治30年(1897)、大陸の福建へ単身赴くこととなる。武術を学ぶための渡航ともいわれるが、直接的には、翌年施行されることとなっていた日本政府による徴兵忌避が理由であったとも言われているようだ。当時、そうした者が少なくないようで、完文が渡った福建・福州市内で入門した湖城道場では、そのような沖縄人が他にもいたことが語られている。
ほどなくして、湖城道場を去ることとなった完文は(一説に師範代との不和が原因とも)、どのような経緯からか現地の武術家シュウサブに師事し、後の上地流の原形となる武術を学ぶ。完文自身が語ったところでは、シュウサブの元で完文は始め三戦(サンチン)だけをひたすら3年間稽古させられ、その後、熱意を認められて正式入門がかなった後、現在の上地流の根幹となる三戦、十三(セーサン)、三十六(サンセーリュー)の型や様々な練功法、薬方などを学んだという(後の調査によって、「シュウサブ」に相当する武術家として、現地で南派少林拳を伝えた周子和の名が挙げられている。周子和は鶴拳や虎拳など、数々の武術を学び、伝えた。特に虎拳を得意とし、鶴拳は非常に精密であったという)。
福建へ渡って7年目となる明治36年(1904)、シュウサブから免許皆伝を許された完文は、2年後にシュウサブの薦めで独立。福建の南せんで、当時の武術家がそうであったように、街頭における薬売りとなって武芸を披露しながら商売を営み、帰郷までの約6年間を武術家として活動する。その後、明治43年(1910)2月、沖縄へ帰郷した完文は、しかし、自らが武術家であることを公言しなかった。それは福建時代、己の弟子が人を殺めてしまったからだといわれる。また、兵役忌避者であったため、帰郷当初は中国人として振る舞っていたという。同年5月、故郷・伊豆味で妻帯した完文は、翌明治44年(1911)、後に上地流を大成することとなる長男・完英を授かる(大正11年〔1922〕には次男、完清が誕生している)。
伊豆味での完文は専ら農業に従事していたが、大正13年(1924)、日之丸産業株式会社の紡績工場へ就職するため、家族を残して単身、和歌山県手平町へ移住する。沖縄出身者の多い同地で、県人会に出入りする者に完文が武術の達人であることを知る人々から教えを請われた完文は、初めは固持していたが遂に彼らの説得に応じ、大正15年(1926)より沖縄出身の少数の者たちを対象に、工場内の社宅で武術の指導を開始する。翌年、郷里を離れた子息、完英も完文へ入門した。
これを契機に、昭和7年(1932)には手平町の昭和通りに「パンガヰヌーン流空手術研究所」を開設(パンガヰヌーン流とは「半硬軟流」の意と説明される)、一般に向けた教授が開始された。この頃、学んだ弟子たちには、現在につながる上地流の各会派の創始者も多い。こうして完文は戦前、戦中まで和歌山の地で空手指導者として過ごした。
終戦後間もない昭和21年(1946)、完文は和歌山の道場を高弟の友寄隆優に託して沖縄へ帰郷。沖縄では、昭和12年(1937)に完文より免許皆伝を受け、大阪から兵庫県尼崎で改名した「上地流空手術研究所」を開設、昭和17年(1942)には沖縄へ帰郷していた完英が、移転地の名護で上地流を指導していた。また、完文の帰郷に前後して、その教え子たちも次々と帰郷し、沖縄各地で完文から学んだ上地流を指導しだした。
こうして上地流の伝承が沖縄にて本格的に始まる中、昭和23年(1947)11月25日、国頭郡・伊江島で隠居生活を過ごしていた完文は、静かに享年71歳の生涯を閉じた。
(参考:沖縄空手流派研究事業『上地流解説書』日本語版)