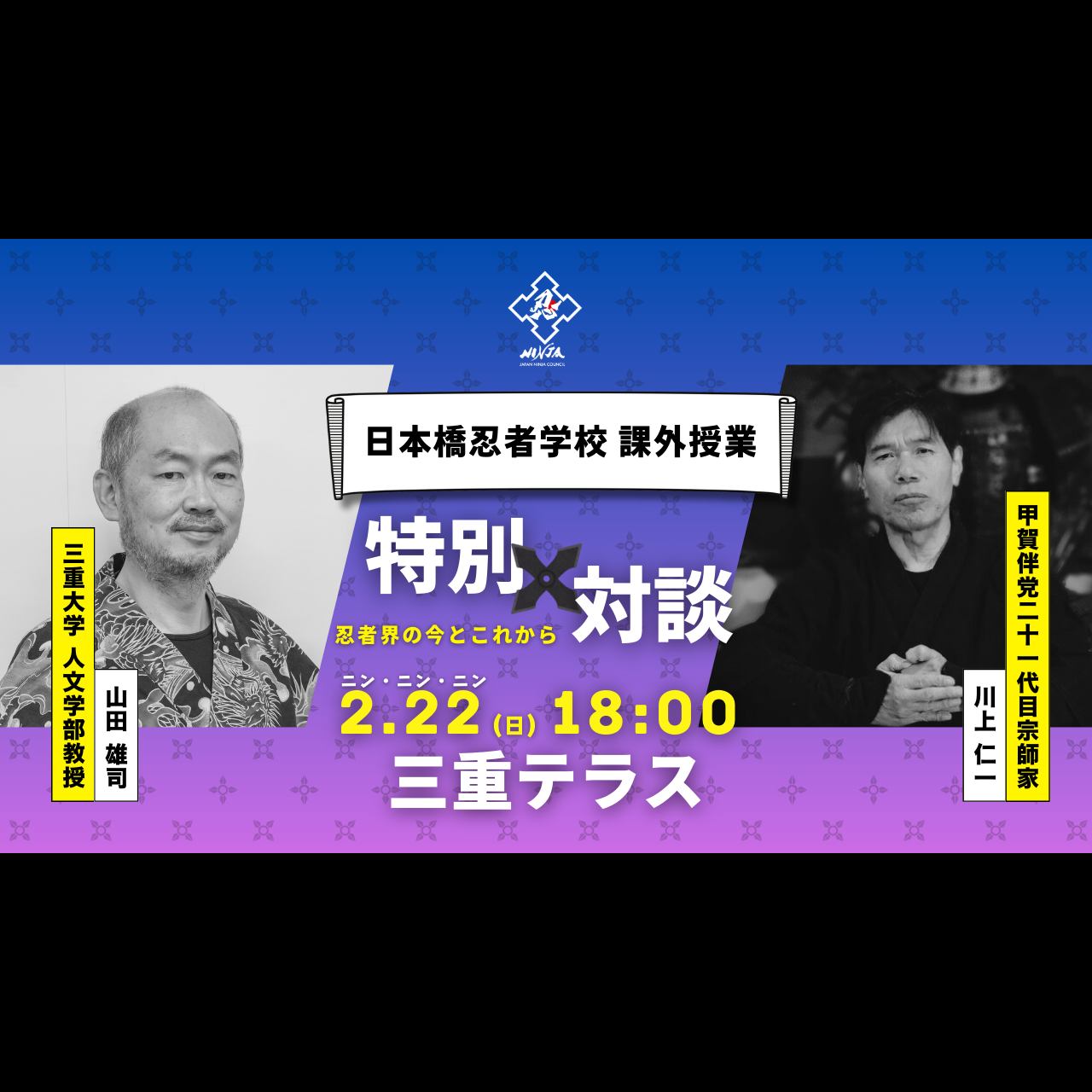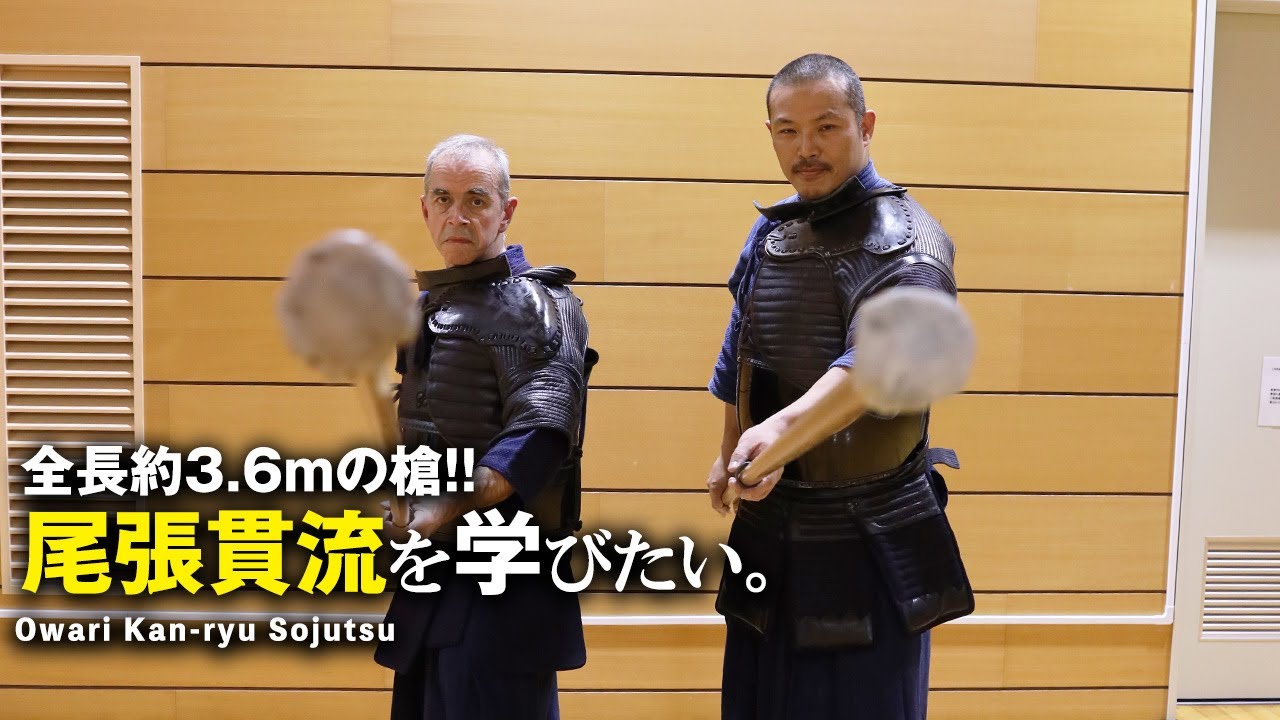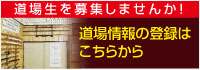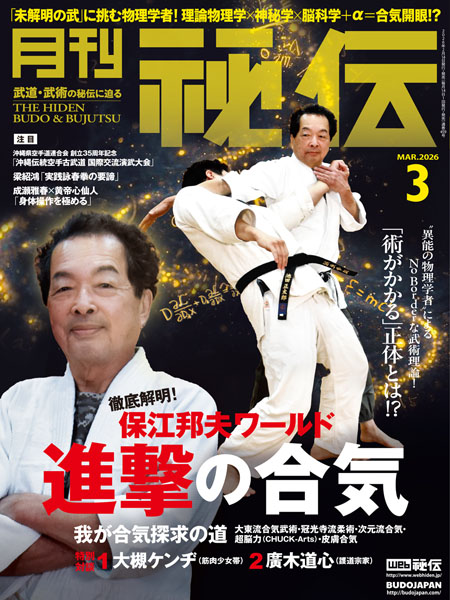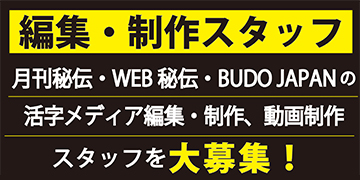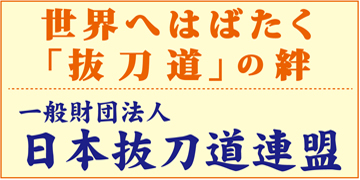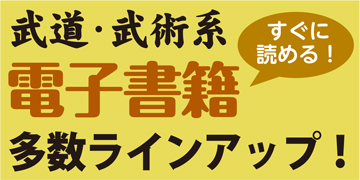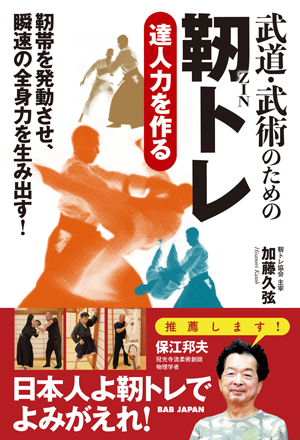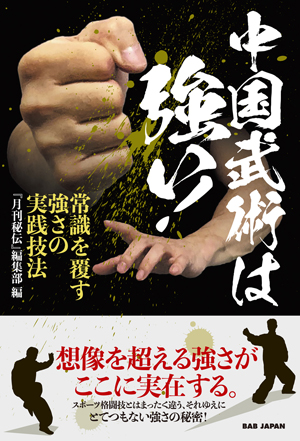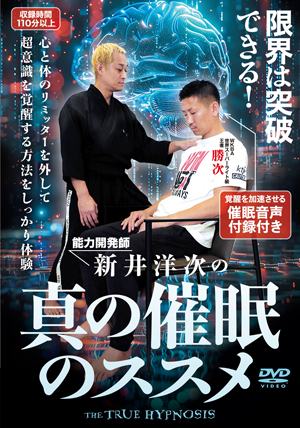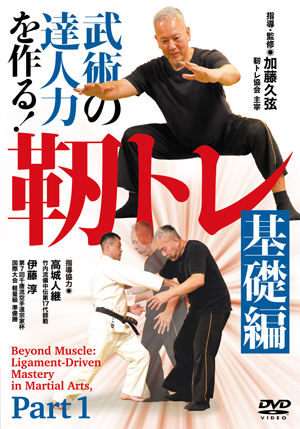本年(平成28年)12月21日、糸東流空手道正修館館長 西田稔師範が、急性白血病のため御逝去されました。享年75歳。
本年(平成28年)12月21日、糸東流空手道正修館館長 西田稔師範が、急性白血病のため御逝去されました。享年75歳。
西田師範は昭和16年、愛媛県大洲生まれ。12歳の頃より、現在では拳道学として著名な大西栄三師範の元で本格的に空手を習い始める。この大西師範の縁で、糸洲安恒の高弟である修道館・遠山(親泊)寛賢師範に師事。その数年後の昭和36年、再び大西師範の縁で、東恩納寛量の高弟である東恩流・許田重発師範に師事した。
昭和36年、若干20歳の頃に、東京都は十条に自らの道場である正修館を開き、修練を重ねる。その後、仕事の関係で一時期大阪に住むことになり、このとき、大阪に居を構える「糸東流二代目宗家の故・摩文仁賢榮」と出会うこととなる。摩文仁賢榮宗家は糸洲と東恩納から学んだ糸東流流祖・摩文仁賢和の長男である。昭和27年の賢和没後、二代目宗家として、また武道家として、体力気力ともにまさに油が乗っている賢榮宗家の空手を見た瞬間、自分が習ってきた首里手・那覇手と同じだと西田師範は直観し、摩文仁糸東流門下となった。
 遠山(親泊)寛賢師範、許田重発師範、摩文仁賢榮師範と、首里手と那覇手を本土に伝えた沖縄空手の大家たちから空手を学んだ西田師範。以後、一生を空手に注ぎ、その本質を求め続け、師の教えに沿って錬り続けたその術は、沖縄の手の、首里手と那覇手の、本質そのままを正統に伝えるものであった。
遠山(親泊)寛賢師範、許田重発師範、摩文仁賢榮師範と、首里手と那覇手を本土に伝えた沖縄空手の大家たちから空手を学んだ西田師範。以後、一生を空手に注ぎ、その本質を求め続け、師の教えに沿って錬り続けたその術は、沖縄の手の、首里手と那覇手の、本質そのままを正統に伝えるものであった。
(糸東流本部・養秀館にて[平成24年撮影]
前列:右端から西田稔師範、小林真一師範、故・摩文仁賢榮二代目宗家、摩文仁賢雄三代目宗家)
戦後の日本復興とともに激動の昭和期を経て、正修館は平成28年には道場創立55周年を迎えた。現在、正修館道場は、関東を中心に全国に支部を持ち、海外にも支部や友好道場がある。西田師範は平成20年刊行の『沖縄空手古武道事典』(柏書房)に糸東流を代表する空手家として紹介され、形(型)の演武写真も掲載されている。
 西田師範は本土、四国の出身であるが、本土に正統な沖縄空手が伝承され、それに触れた最初の世代である。その意味で西田師範は、「本土に伝承された沖縄正統空手」最後の伝承者、"ラスト・オブ・ファーストジェネレーション─最後の第一世代"である。武の神、空手の神に見初められたとしかいいようがない西田師範の空手探求の旅の詳細については、本誌2016年4月号記事「本土における沖縄正統空手の系譜」にて、正修館柏道場 小林真一師範、同・湯川進太郎準師範に紹介いただいた。
西田師範は本土、四国の出身であるが、本土に正統な沖縄空手が伝承され、それに触れた最初の世代である。その意味で西田師範は、「本土に伝承された沖縄正統空手」最後の伝承者、"ラスト・オブ・ファーストジェネレーション─最後の第一世代"である。武の神、空手の神に見初められたとしかいいようがない西田師範の空手探求の旅の詳細については、本誌2016年4月号記事「本土における沖縄正統空手の系譜」にて、正修館柏道場 小林真一師範、同・湯川進太郎準師範に紹介いただいた。
(12月3日に開催された正修館創立55周年の記念祝賀会にて。
右:湯川進太郎師範、中央:西田稔師範、左:小林真一師範)
改めまして、西田稔師範の御冥福をお祈り申し上げます。